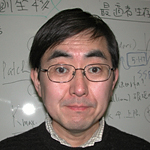| |
鳥の脳、行動、知能 :エイリアンを探して
古生代の石炭紀、鳥類の祖先は我々哺乳類の祖先から枝分かれしました。 その後の約3億年の間、彼らと我々は独立な進化の道を歩んできました。その過程で我々は大脳皮質を肥大化させ、彼らは大脳外套を肥大化しました。どちらも巨大な大脳の持ち主です。特に、一部の鳥類(特にスズメ目カラス科)と一部の哺乳類(特に霊長目ヒト科)との間には、その行動と知能とに、驚くべき収束(並行進化)が見られます。まったく異なる起源の脳を持ながら、同じような進化的淘汰圧が良く似た認知機能を進化させたと考えられています。しかし、彼らトリの知能の構成原理を我々はまだ知りません。宇宙から来たエイリアンの如く、鳥の脳は暗黒の中にいます。
採餌決定と意志、価値評価
では、ヒトの知能の構成原理は分かっているのでしょうか?答えは「否」です。心理学や精神医学の膨大な研究成果は、確かに多くの知見を蓄えて人間の「生理学的な素顔」 を暴き出してきました。言語、感情、記憶など、心のメカニズムの多くがサイエンスの対象となったのです。しかし、「生物学的な素顔」つまり心の究極要因(「なぜこのような認知機能が生まれてきたのか?」、「この心の働きには、どのような進化的意義があるのか」)は不問に付されてきました。
私の研究室は、採餌決定にそのカギがあると考えて、研究を進めています。餌を効率よく採取できる動物は、より速く成長しより長い繁殖期を謳歌して、より高い適応度を実現します。しかし、餌はいつでも目の前にあるわけではない。目の前の餌はあまりに小さいかもしれない。良い採餌者は、目の前の小さな餌をまたぎ越して、より遠くのより大きな餌を目指すことができなくてはいけません。それが客観的に良い餌であることを正しく評価する知能が必要です。採餌行動の中で動物が示す行動は、その進化的起源に依らず同じ淘汰圧を、このように強く受けているはずです。
衝動性と社会的知性、ゲームの理論
採餌決定を支配する脳部位を見出し、その神経回路の挙動を研究してきました。ニワトリのヒヨコを対象として行ってきた研究の成果です。その結果、客観的な餌の価値評価と、動物の選択から推定される主観的価値評価の間には、かなり深刻なギャップがあることがわかってきました。たとえば、3秒後にもらえる6粒の粟は、目の前に置かれた1粒の粟より、ヒヨコにとっては劣る餌なのです。また、その量が「ある時は0粒、ある時は10粒」と変動する場合、同じ価値を持つのは「いつでも3粒」の餌場になります。数学的な期待値とは一致しないのです。客観的な価値の正しい評価系であるべき採餌決定のシステムは、何かしら別の因子によって歪められ、動物は経済的な利益の最大化から追い立てられています。「ヒヨコは粟のみにて生きるにあらず」、これが我々がヒヨコから学んだことでした。では、何がヒヨコを経済的な合理性から(つまり、エサとモノの世界から)逸脱させているのでしょうか?
ここに社会性というものが持つ基本的な意味があると考えています。3秒後の餌は、あなたが来てついばんでしまうかもしれない。そのような他者がいる世界では、目の前の1粒を確保することが合理的です。動物は物質的な世界にだけ生きているのではありません。経済的な合理性からの逸脱は、社会的に正しい選択へと、動物をいざなう重要な機構となっているのかもしれません。
今後の研究課題は、利益とコストを計算する脳内の神経回路を同定することにあります。いわばデフォルトとして、「経済的合理性」の脳科学を行っています。さらに将来の課題として、他者の存在による「合理性」からの踏み外しを問題とします。多くの鳥類が、近縁個体への給餌などの利他行動を行います。あるいは共同行為を組織して、互恵的な行為を行います。認知科学、実験心理学、システム神経生理学、数理科学、経済学、行動生態学、いくつもの手法と考えを統合的に使いこなして、研究を進めていきます。 |